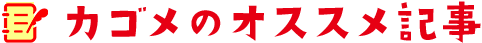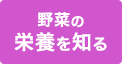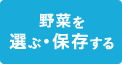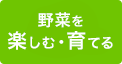こどもの日とは?意味は?
1948年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた、国民の祝日(※1)のひとつです。「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福を図るとともに、母に感謝する」日とされています。
1 祝日法の制定時に「国民の祝日」とされたのは、次の9日でした。元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)
端午の節句とは?
もともと中国で始まった風習で、日本では平安時代から受け継がれています。子どもの健康や健やかな成長を願い、五月人形や鎧兜(よろいかぶと)、こいのぼりを飾ります。

こどもの日の食べ物や風習に込められた意味
こどもの日に食べたり飾ったりするものには、子どもの成長を願う気持ちが込められています。
●ちまき
「笹巻き」とも呼ばれ、端午の節句の供物として中国から伝わったといわれています。子どもの健やかな成長を願って食べられます。
●柏餅
柏は、昔から神聖な木としてまつられてきました。また、柏の葉は新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、親から子、孫へと命がつながる縁起物として考えられ子どもの日に食べられるようになりました。
●こいのぼり
鯉は池や沼地でも生きられる生命力の強い魚。鯉が滝を上って竜になり天にのぼるという中国の「登竜門」の言い伝えになぞらえ、子どもに健康ですくすくと育ってほしいという気持ちが込められたと言われています。
・その他の節句
ひな祭りの由来や食べ物はコチラ
七夕祭りの由来や食べ物はコチラ
こどもの日に作りたい旬の野菜を使ったレシピ
こどもの日の食べ物はちまきや柏餅が有名ですが、たけのこは成長が早く、天に向かって真っすぐにすくすくと伸びることから、端午の節句のお祝い料理に使われます。たけのこのレシピを紹介します。
●たけのこご飯
たけのこの食感と和風の味付けが相性良し!

材料(2人分)
- たけのこ:80g
- 米:3合
- 油揚げ:1枚
- 鶏肉:100g
- 木の芽(お好みで):4枚
- だし(米の量の2割増し):720ml
[A]
- 酒:大さじ2
- 醤油:大さじ3
作り方
- 米は洗ってザルにあげ、1時間程度おく。
- たけのこは、長さ2cmの短冊切りにする。油揚げも同様に切る。
- 鶏肉は、5mm角に切る。
- ボウルにAを合わせ、2と3を約10分漬けて、下味を付ける。
- 1とだしを炊飯器に入れ、4の具を漬け汁ごと加えて炊く。
- ご飯を10分程蒸らしたら、底の方から軽く混ぜて器に盛り付け、お好みで木の芽をあしらう。
・その他のたけのこレシピ
たけのこの煮物レシピはコチラ
たけのこの天ぷらや、グラタンレシピはコチラ
最後に
こどもの日の由来を知って、旬のたけのこご飯を楽しんでください。
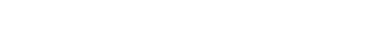
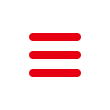








![[枝豆の茹で方]プロ直伝のおいしく茹でるコツと、簡単レシピ! [枝豆の茹で方]プロ直伝のおいしく茹でるコツと、簡単レシピ!](/library/vegeday/img/article/201906/img_9899_main.jpg)
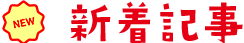


![トマト栽培&育て方[準備と植付け]プランターで家庭菜園入門! トマト栽培&育て方[準備と植付け]プランターで家庭菜園入門!](/library/vegeday/img/article/201704/img_6746_main.jpg)